みなさんは、「母子登校」という言葉をしっていますか?
小学校低学年のお子さんに多く見られる母子登校。
周囲からは「学校に来れているだけでいいじゃない」「まだママに甘えたい時期なのね」と言っていただくものの、お母さんとしてはどうしても周りのお子さんとわが子を比べてしまいやすいです。
不登校ではないけれど、登校の面において課題や不安がある状態です。
お母さんの負担がとても大きいのが特徴で、頑張るお母さんが疲れてしまいやすいんです。
「子どものことを考えれば、これくらいの労力は仕方がない」とおっしゃる方もいます。
子が宝ならお母さんも宝。
水野先生はいつもこのようにおっしゃっていますが、親子が共にしんどくなりすぎないのが私は大事だなと思います。
根性論ではどうにもならない時もあるのが母子登校です。
そんな母子登校について、まいどん先生が解説をいたします
母子登校といっても、深刻度合いは様々です。
レベル1、校門まで一緒に登校(子どもはお母さんとは学校外で別れられる)
レベル2、下駄箱や教室の外まで一緒に登校(お母さんが学校内には入るが教室までは入らない)
レベル3、教室まで一緒に入り、朝の会まではお母さんが一緒にいないと不安
レベル4、お母さんが校内にいないと不安なので、子どもが落ち着くまでお母さんは別室待機
レベル5、お母さんとずっと一緒にいないと不安なので、教室あるいは別室でお母さんと授業を受ける
あえてわかりやすくするようにレベル分けにしましたが、このように5に近づけば近づくほど母子依存(子どもがお母さんに依存してしまう状態)が強く、母子登校の解消が難しいとされます。
また、母子登校になったお子さんは予兆として朝行き渋りを見せます。
始めはお母さんも叱ったりなだめたりしながらなんとか登校させるのですが、どこかのタイミングでお母さんも「これはちょっと一緒に行ってあげないとどうしようもないな」と判断される時がやってきます。
例えば、近所迷惑になるくらい大声で何十分も泣かれたり、子どもが泣きじゃくって辛そうにしていたり、「お母さんと一緒なら行くから!」と登校の意思が見える時にお母さんが子どもについて行こうと決められることが多いです。
行き渋りの原因がその日の「授業が不安」「給食が不安」と1日限りの不安ごとや悩み事だったとすれば、一度ついていって不安を解消してやればその後は1人でいつも通りに登校が出来るケースもあります。
しかしながら、大体のケースでは本人の自立の問題に起因することが多く、根本的な原因を解決していかなければ母子登校は深刻化しやすいのが現状です
その他登校をめぐる状況について、日本財団 不登校傾向にある子どもの実態調査より、学校生活をめぐる子どもの特徴(タイプ)6群を引用しておりますので参考までにご覧ください。

母子登校はこの図で言えば②〜⑤の状態です。
お母さんと一緒に登校は出来ているとは言っても、不登校に発展しやすい状況ともいえます。
1、お子さんの自立面に課題がある
2、お母さんが共依存状態にある
3、お子さんの発達に課題がある
4、環境に起因する問題
1の「お子さんの自立面に課題がある」については、私たちのブログで過去に発信した内容を参考になさってください(「母子依存」、「小1プロブレム」、「過干渉」、「過保護」など)
家庭内で親御さんがお子さんに対して、年齢相応の自立心をはぐくむ家庭教育を意識されているかどうかで、お子さんの自立度合いは大きく変わります。
水野先生の新刊『子どもには、どんどん失敗させなさい』わが子が12歳になるまでに知っておきたい「自信あふれる子」の育て方 (PHP研究所)で、特に詳しく書かれてあるのでご興味がある方は是非ご覧ください♪
2の「お母さんが共依存状態にある」についてですが、
つまり、お母さん自身が「『子どもが自分を必要としている』と実感することで自分の存在意義を見出している状態」とも言えます。
子どもがお母さんを頼る状態を作り出したい気持ちから、お母さんが子どもに対して過保護になりやすく、小学1年生ならその年の子であれば出来る子ともお母さんが先回りをして子どもの代わりに対応してあげたりすることが多く見られます
「あなたは何も出来ないんだから」といいながらも、心の中で「自分は必要とされている」と感じてしまう状態を指します。このような状態にあるケースでは、まずお母さん自身が子どもから精神的に離れることに慣れるのを目指すことが支援の中では多いです。
3の「お子さんの発達に課題がある」の場合は、お子さんが実は発達障がいであったり、学校環境に適応できない理由があることに気づいていないケースです。
学習についていくことが困難、聴覚過敏(音が聴こえすぎてしまう)、多動傾向、自閉傾向 などの傾向があるお子さんの場合は、どうしても年齢が重なるごとに周囲との集団生活が困難になりやすいです。
実は発達に課題があるお子さんであった場合は適切な支援を早い段階で受けておいたほうが、後々様々なサポートを受けやすくなります。
しかしながら、昨今は発達障がいへの理解が進みすぎて、実は発達障がいではないケースでも「○○障がいのグレーゾーン」と言われてしまうことは多いです。
基本的に発達障がいは、生まれ持ってのもの(先天性)であり、子育ての良し悪しでなるもの(後天性)ではありません。
「おとなになって発達障がいになった」と言う話もよく聞きますが、実はそれは生まれ持ってそういった障がいをもっていたけれども、本人が気づかず、大人になってからご自身が障がいをもっておられたことに気づいたということです。
グレーゾーンというのは限りなくグレーで、結局のところはそれらは個性であり、教育のゴールは「子どもが将来社会に出て困らないようにスキルや社会のルールを教えてあげる」ことです。
障がいという言葉にとらわれ過ぎてしまうと、本来教えられるものも教えられなくなることもありますので、安易に発達障がいと判断はしないことをお勧めします。
4の環境に起因する問題とは、学校の先生やクラスメイトとの相性や、通学路の遠さなどが挙げられます。
母子登校の原因は上記にもあるように様々です。
どのパターンによるものかを見極めなければ、とんちんかんな対応を取ってしまうことになり、母子登校が深刻化しやすいです。
まずは落ち着いて状況分析をしてみましょう。
2の「母子登校の原因とは」で書かせていただいた4つの中から、お子さんの母子登校がどのパターンに当てはまるかを考えていきましょう。
1、お子さんの自立面に課題がある
母子登校のケースで最も多くみられるのがこのパターンです。
小学1年生のお子さんが、45分間じっとして座っていられなかったり、お母さんにどうすればいいかを聞かないと不安になったり、お母さんと一緒にいないと不安といったケースでは、多くの場合は自立面に問題があります。
家庭の中で、いかに学校生活に適応できるかという点がとても大切であり、家庭内での生活と学校生活
でのギャップがないようにしましょう。
なんでもお母さんに「これどうしたらいい?」と聞かれたとき、例えば「これはこうするのよ」と教えてあげるのも大切ですが、前に教えていることであれば「この前どうしたかな?」と思い出させてみたり、「どうするのがいいと思う?」と考えさせてみることも大切です。
そのような対応の繰り返しにより、自分で考えて行動が出来るような子になっていきやすいです。
家庭で自立を育む家庭教育を実践しながら、「学校は行くもの」として親御さんは対応をしていくことが大切です。自立を育む家庭教育の積み重ねにより、子ども自身「お母さんについてきてもらうことが恥ずかしい」と思えるようになっていくのが理想です。
過去の「母子依存」についてのブログでも、このような自立を育む家庭教育について記事を発信していますので、参考になさってくださいね。
2、お母さんが共依存状態にある
まずはお母さんが子離れすることを目指していきましょう。
共依存状態にある場合、お母さんは四六時中子どもの行動をすべて見て管理しようとしがちです。
見てしまうと、どうしても声をかけたくなるものなので、まずは「極力本人に任せられることを増やして、お母さんは子どもの行動すべてを見ないようにする」ことを目指していきましょう。
ときにお友達とカフェにいったり、子どもがいない別室でのんびり読書をしてもかまいません。
「そんなことしたら子どもがさみしがる!かわいそう!」
そんな風に思う必要もありません。
お母さんが1人の時間を持つ、作るのって、とっても大切なんですよ
3、お子さんの発達に課題がある
この見極めはとても難しいです。
実際に医療機関にいけば、上記にもあるように「グレーゾーン」と言われてしまうことも可能性としてあるかもしれません。
しかし、そこは先をまずは考えてみましょう。
「この子には個性がある。そして、この個性を持って社会に出ていかなければならない。」ということです。
苦手分野を、ある程度得意に出来るように教えたり乗り越えさせるべきか?
「自分はこれが苦手です。だから手伝ってほしいです」と周囲に理解や協力をお願いできるようにさせるべきか?
自分の得意分野を見つけて、その道で極めて自信をもたせるべきか?
など、方法は様々です。
じっくり考えて答えを出されることをおすすめします。
4、環境に起因する問題
これらについては学校と相談して協力体制を作るということも大切かと思います
どうしても学校との連携が難しければ、市の相談窓口や教育委員会に相談してみるのもひとつです。
ご家庭だけで抱え込まないように気をつけましょう。
子どもの自立に重きを置いた家庭教育が出来ているかどうかで、様々な問題(家庭内暴力、子どものメンタル不調、夫婦間不和 など)は予防できます。
どこまでやると過干渉や過保護のケースに当てはまるのか、何を教えてあげればいいのか、必要な干渉と過干渉のライン引きをしっかりと行うことが大切です。
なってから対応をするのは大変ですが、生活習慣病と同じで母子登校は予防ができます。
さらに家庭教育の実践で子どもは伸びます。
・母子登校は登校出来ているとは言っても深刻な状況と言える
・母子登校の原因は様々である
・母子登校は予防できる
今回は母子登校について詳細に解説いたしましたが、如何だったでしょうか。
私達の支援を過去に受けられた親御さんで、もし周りに母子登校で悩まれている方が居れば是非今回のブログの内容を参考にアドバイスをしていただきたいなと思います。
母子登校で悩み私達のもとへご相談いただくケースは年々増加しており、多くの親御さんは電話越しに泣きながらお話いただくことがほとんどです
ご主人がお仕事が忙しくて頼れない、自分の子育てが悪かったからこうなったんだとご自身を責めておられる方も多いです
決してお母さん1人に責任があるわけでも、子育てだけが原因ではありません。
子育ては1人で行うものでもなく、周囲に頼りながら皆で育てるというイメージで行っていいんです。
どうか、全部背負ってつらい思いをしないでください。
支援者として、少しでもこのような悩みを抱え泣いてご相談いただく親御さんが減っていけばいいなと感じております。
だからこそ、家庭教育を広めていきたいです。
みなさんも、是非家庭教育の普及活動にご協力ください。
下にリンクを貼っておりますので、少しでも子育てに悩まれている方がいましたらお役立てください。
それでは、また次回ブログ記事にてお会いしましょう
家庭教育についてまなぶ
・本でまなぶ

↑Amazonでポチっとお買い求めください!
・イラストでまなぶ
↑イラストでまなぶ家庭教育!
・動画でまなぶ

↑カテイズムオンラインスクールでわかりやすく家庭教育をまなぼう!
・YouTubeでも動画配信を行っております!(チャンネル登録よろしくお願いします!)
まいどん先生
(↓下のバナーをポチッと応援お願いします )
)
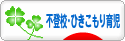
↓最新記事がアップされるたびに通知がきます♪お手軽LINE読者登録はこちらから↓

(↓支援にご興味がある方はこちら↓)

小学校低学年のお子さんに多く見られる母子登校。
周囲からは「学校に来れているだけでいいじゃない」「まだママに甘えたい時期なのね」と言っていただくものの、お母さんとしてはどうしても周りのお子さんとわが子を比べてしまいやすいです。
不登校ではないけれど、登校の面において課題や不安がある状態です。
お母さんの負担がとても大きいのが特徴で、頑張るお母さんが疲れてしまいやすいんです。
「子どものことを考えれば、これくらいの労力は仕方がない」とおっしゃる方もいます。
子が宝ならお母さんも宝。
水野先生はいつもこのようにおっしゃっていますが、親子が共にしんどくなりすぎないのが私は大事だなと思います。
根性論ではどうにもならない時もあるのが母子登校です。
そんな母子登校について、まいどん先生が解説をいたします
1、母子登校とは
「母子登校」とは、字のごとくお母さんと子どもが一緒に登校することを指します。母子登校といっても、深刻度合いは様々です。
レベル1、校門まで一緒に登校(子どもはお母さんとは学校外で別れられる)
レベル2、下駄箱や教室の外まで一緒に登校(お母さんが学校内には入るが教室までは入らない)
レベル3、教室まで一緒に入り、朝の会まではお母さんが一緒にいないと不安
レベル4、お母さんが校内にいないと不安なので、子どもが落ち着くまでお母さんは別室待機
レベル5、お母さんとずっと一緒にいないと不安なので、教室あるいは別室でお母さんと授業を受ける
あえてわかりやすくするようにレベル分けにしましたが、このように5に近づけば近づくほど母子依存(子どもがお母さんに依存してしまう状態)が強く、母子登校の解消が難しいとされます。
また、母子登校になったお子さんは予兆として朝行き渋りを見せます。
始めはお母さんも叱ったりなだめたりしながらなんとか登校させるのですが、どこかのタイミングでお母さんも「これはちょっと一緒に行ってあげないとどうしようもないな」と判断される時がやってきます。
例えば、近所迷惑になるくらい大声で何十分も泣かれたり、子どもが泣きじゃくって辛そうにしていたり、「お母さんと一緒なら行くから!」と登校の意思が見える時にお母さんが子どもについて行こうと決められることが多いです。
行き渋りの原因がその日の「授業が不安」「給食が不安」と1日限りの不安ごとや悩み事だったとすれば、一度ついていって不安を解消してやればその後は1人でいつも通りに登校が出来るケースもあります。
しかしながら、大体のケースでは本人の自立の問題に起因することが多く、根本的な原因を解決していかなければ母子登校は深刻化しやすいのが現状です
その他登校をめぐる状況について、日本財団 不登校傾向にある子どもの実態調査より、学校生活をめぐる子どもの特徴(タイプ)6群を引用しておりますので参考までにご覧ください。

母子登校はこの図で言えば②〜⑤の状態です。
お母さんと一緒に登校は出来ているとは言っても、不登校に発展しやすい状況ともいえます。
2、母子登校の原因とは
原因として考えられる理由は様々ですが、代表的なものとしては以下の4つが挙げられます。1、お子さんの自立面に課題がある
2、お母さんが共依存状態にある
3、お子さんの発達に課題がある
4、環境に起因する問題
1の「お子さんの自立面に課題がある」については、私たちのブログで過去に発信した内容を参考になさってください(「母子依存」、「小1プロブレム」、「過干渉」、「過保護」など)
家庭内で親御さんがお子さんに対して、年齢相応の自立心をはぐくむ家庭教育を意識されているかどうかで、お子さんの自立度合いは大きく変わります。
水野先生の新刊『子どもには、どんどん失敗させなさい』わが子が12歳になるまでに知っておきたい「自信あふれる子」の育て方 (PHP研究所)で、特に詳しく書かれてあるのでご興味がある方は是非ご覧ください♪
2の「お母さんが共依存状態にある」についてですが、
共依存(きょういそん、きょういぞん、英語: Co-dependency)、共嗜癖(きょうしへき、Co-addiction)とは、自分と特定の相手がその関係性に過剰に依存しており、その人間関係に囚われている関係への嗜癖状態(アディクション)を指す。 すなわち「人を世話・介護することへの依存」「愛情という名の支配」である。 ≪引用:Wikipedia≫
つまり、お母さん自身が「『子どもが自分を必要としている』と実感することで自分の存在意義を見出している状態」とも言えます。
子どもがお母さんを頼る状態を作り出したい気持ちから、お母さんが子どもに対して過保護になりやすく、小学1年生ならその年の子であれば出来る子ともお母さんが先回りをして子どもの代わりに対応してあげたりすることが多く見られます
「あなたは何も出来ないんだから」といいながらも、心の中で「自分は必要とされている」と感じてしまう状態を指します。このような状態にあるケースでは、まずお母さん自身が子どもから精神的に離れることに慣れるのを目指すことが支援の中では多いです。
3の「お子さんの発達に課題がある」の場合は、お子さんが実は発達障がいであったり、学校環境に適応できない理由があることに気づいていないケースです。
学習についていくことが困難、聴覚過敏(音が聴こえすぎてしまう)、多動傾向、自閉傾向 などの傾向があるお子さんの場合は、どうしても年齢が重なるごとに周囲との集団生活が困難になりやすいです。
実は発達に課題があるお子さんであった場合は適切な支援を早い段階で受けておいたほうが、後々様々なサポートを受けやすくなります。
しかしながら、昨今は発達障がいへの理解が進みすぎて、実は発達障がいではないケースでも「○○障がいのグレーゾーン」と言われてしまうことは多いです。
基本的に発達障がいは、生まれ持ってのもの(先天性)であり、子育ての良し悪しでなるもの(後天性)ではありません。
「おとなになって発達障がいになった」と言う話もよく聞きますが、実はそれは生まれ持ってそういった障がいをもっていたけれども、本人が気づかず、大人になってからご自身が障がいをもっておられたことに気づいたということです。
グレーゾーンというのは限りなくグレーで、結局のところはそれらは個性であり、教育のゴールは「子どもが将来社会に出て困らないようにスキルや社会のルールを教えてあげる」ことです。
障がいという言葉にとらわれ過ぎてしまうと、本来教えられるものも教えられなくなることもありますので、安易に発達障がいと判断はしないことをお勧めします。
4の環境に起因する問題とは、学校の先生やクラスメイトとの相性や、通学路の遠さなどが挙げられます。
3、母子登校になった場合
まずは分析をしっかり行うことが大切です。母子登校の原因は上記にもあるように様々です。
どのパターンによるものかを見極めなければ、とんちんかんな対応を取ってしまうことになり、母子登校が深刻化しやすいです。
まずは落ち着いて状況分析をしてみましょう。
2の「母子登校の原因とは」で書かせていただいた4つの中から、お子さんの母子登校がどのパターンに当てはまるかを考えていきましょう。
1、お子さんの自立面に課題がある
母子登校のケースで最も多くみられるのがこのパターンです。
小学1年生のお子さんが、45分間じっとして座っていられなかったり、お母さんにどうすればいいかを聞かないと不安になったり、お母さんと一緒にいないと不安といったケースでは、多くの場合は自立面に問題があります。
家庭の中で、いかに学校生活に適応できるかという点がとても大切であり、家庭内での生活と学校生活
でのギャップがないようにしましょう。
なんでもお母さんに「これどうしたらいい?」と聞かれたとき、例えば「これはこうするのよ」と教えてあげるのも大切ですが、前に教えていることであれば「この前どうしたかな?」と思い出させてみたり、「どうするのがいいと思う?」と考えさせてみることも大切です。
そのような対応の繰り返しにより、自分で考えて行動が出来るような子になっていきやすいです。
家庭で自立を育む家庭教育を実践しながら、「学校は行くもの」として親御さんは対応をしていくことが大切です。自立を育む家庭教育の積み重ねにより、子ども自身「お母さんについてきてもらうことが恥ずかしい」と思えるようになっていくのが理想です。
過去の「母子依存」についてのブログでも、このような自立を育む家庭教育について記事を発信していますので、参考になさってくださいね。
2、お母さんが共依存状態にある
まずはお母さんが子離れすることを目指していきましょう。
共依存状態にある場合、お母さんは四六時中子どもの行動をすべて見て管理しようとしがちです。
見てしまうと、どうしても声をかけたくなるものなので、まずは「極力本人に任せられることを増やして、お母さんは子どもの行動すべてを見ないようにする」ことを目指していきましょう。
ときにお友達とカフェにいったり、子どもがいない別室でのんびり読書をしてもかまいません。
「そんなことしたら子どもがさみしがる!かわいそう!」
そんな風に思う必要もありません。
お母さんが1人の時間を持つ、作るのって、とっても大切なんですよ
3、お子さんの発達に課題がある
この見極めはとても難しいです。
実際に医療機関にいけば、上記にもあるように「グレーゾーン」と言われてしまうことも可能性としてあるかもしれません。
しかし、そこは先をまずは考えてみましょう。
「この子には個性がある。そして、この個性を持って社会に出ていかなければならない。」ということです。
苦手分野を、ある程度得意に出来るように教えたり乗り越えさせるべきか?
「自分はこれが苦手です。だから手伝ってほしいです」と周囲に理解や協力をお願いできるようにさせるべきか?
自分の得意分野を見つけて、その道で極めて自信をもたせるべきか?
など、方法は様々です。
じっくり考えて答えを出されることをおすすめします。
4、環境に起因する問題
これらについては学校と相談して協力体制を作るということも大切かと思います
どうしても学校との連携が難しければ、市の相談窓口や教育委員会に相談してみるのもひとつです。
ご家庭だけで抱え込まないように気をつけましょう。
4、母子登校の予防策とは
母子登校の予防策は、何と言っても家庭教育の実践です。子どもの自立に重きを置いた家庭教育が出来ているかどうかで、様々な問題(家庭内暴力、子どものメンタル不調、夫婦間不和 など)は予防できます。
どこまでやると過干渉や過保護のケースに当てはまるのか、何を教えてあげればいいのか、必要な干渉と過干渉のライン引きをしっかりと行うことが大切です。
なってから対応をするのは大変ですが、生活習慣病と同じで母子登校は予防ができます。
さらに家庭教育の実践で子どもは伸びます。
まとめ
・母子登校はなったご家庭にしか分からない苦労がある・母子登校は登校出来ているとは言っても深刻な状況と言える
・母子登校の原因は様々である
・母子登校は予防できる
今回は母子登校について詳細に解説いたしましたが、如何だったでしょうか。
私達の支援を過去に受けられた親御さんで、もし周りに母子登校で悩まれている方が居れば是非今回のブログの内容を参考にアドバイスをしていただきたいなと思います。
母子登校で悩み私達のもとへご相談いただくケースは年々増加しており、多くの親御さんは電話越しに泣きながらお話いただくことがほとんどです
ご主人がお仕事が忙しくて頼れない、自分の子育てが悪かったからこうなったんだとご自身を責めておられる方も多いです
決してお母さん1人に責任があるわけでも、子育てだけが原因ではありません。
子育ては1人で行うものでもなく、周囲に頼りながら皆で育てるというイメージで行っていいんです。
どうか、全部背負ってつらい思いをしないでください。
支援者として、少しでもこのような悩みを抱え泣いてご相談いただく親御さんが減っていけばいいなと感じております。
だからこそ、家庭教育を広めていきたいです。
みなさんも、是非家庭教育の普及活動にご協力ください。
下にリンクを貼っておりますので、少しでも子育てに悩まれている方がいましたらお役立てください。
それでは、また次回ブログ記事にてお会いしましょう
家庭教育についてまなぶ
・本でまなぶ

↑Amazonでポチっとお買い求めください!
・イラストでまなぶ
↑イラストでまなぶ家庭教育!
・動画でまなぶ

↑カテイズムオンラインスクールでわかりやすく家庭教育をまなぼう!
・YouTubeでも動画配信を行っております!(チャンネル登録よろしくお願いします!)
まいどん先生
(↓下のバナーをポチッと応援お願いします
 )
) ↓最新記事がアップされるたびに通知がきます♪お手軽LINE読者登録はこちらから↓

(↓支援にご興味がある方はこちら↓)

