ブログ読者のみなさんこんにちは
まいどん先生です
新しい学年がスタートし、お子さんだけではなく親御さんもドキドキする時期です
今回は、「失敗経験は必要か?」というテーマについて記事を書かせていただきます。
結論から申し上げると、必要です。
よく、家庭教育支援のご相談では「うちの子はうたれ弱いので前もって指示しておかないと失敗したら学校に行かなくならないか不安で」と言った内容のお話をいただきます。
しかしこれ、自立の観点からすれば逆効果なんです
親御さんが先回りをして「ハンカチ持った?」「ここに置いてたら宿題忘れそうだよ!ランドセルに入れておかないと!」「お箸忘れてるよ!」などと子どもが失敗しないように声をかけ続けると、子どもは失敗を経験しません。
親御さんが懸念されている「失敗経験による行き渋りや不登校の予防」にはなるのかもしれません。
しかしながら、これらの声掛けをし続けることで以下のようなことが起こり得ると考えられます。
・学校生活の中で親が前もって声掛けができない状況で失敗経験をして学校が怖くなる
・誰かに指示されないと行動できなくなる
・失敗からどう立ち上がるかが分からない
・失敗=自分はだめな人間 と極端な考え方になる
・年齢相応に自立ができず、他のお子さんとの差ができていった結果学校が怖くなる
などなど。
わたしたちは、様々な経験をして大人になりました。
その経験は成功体験のみではなかったはずです。失敗もたくさん経験して、「次はこうしてみよう」と考えて行動を積み重ねてきたはずです。
むしろ家庭教育で大切なのは、「失敗おめでとう」と言えるくらい、親御さんが子どもの失敗を愛してあげられるかです
何もしないで失敗しないよりも、チャレンジがあっての失敗のほうが尊いです。
失敗は成功の母とも言えますね。
学齢期にお母さんが常に子どもの隣にいて指示してやることは出来ません。
子どもたちは学校環境において楽しいこと、つらいこと、腹がたつこと、悲しいこと、様々なことを体験して社会を知っていきます。
最低限、「人様に迷惑をかけないように」「ルールを守るように」というところをしつけとして伝えておくだけで実は子どもの自立心はぐんと伸びたりします。
もちろん、新小学1年生の場合はある程度親が一緒に時間割をそろえたり、宿題を見てやったり、教えてやることは大切です。はじめてやることについては親が教えてやることは大事です。
本来であればその学年の子であれば自分で考えて行動できる子なのに、親が先回りしてものを言って失敗経験を積ませないようにするのは、実は将来的にみると子どもが本当に困るときがやってくるかもしれません
詳細については、水野先生の書籍やDVDで解説されているPCM11の項目の「先回りしてものを言って子どもの経験を奪わない」をご覧ください
すべてのご家庭にこの理論が当てはまるわけではなく、周囲のサポートが必要なお子さんもいます。
そこについては保護者の皆さんにご判断いただければと思います。
このブログ記事が皆さんのお役に立てれば幸いです
 まいどん先生
まいどん先生
(下のバナーをポチッと応援お願いします )
)
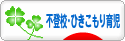
にほんブログ村

まいどん先生です

新しい学年がスタートし、お子さんだけではなく親御さんもドキドキする時期です

今回は、「失敗経験は必要か?」というテーマについて記事を書かせていただきます。
結論から申し上げると、必要です。
よく、家庭教育支援のご相談では「うちの子はうたれ弱いので前もって指示しておかないと失敗したら学校に行かなくならないか不安で」と言った内容のお話をいただきます。
しかしこれ、自立の観点からすれば逆効果なんです

親御さんが先回りをして「ハンカチ持った?」「ここに置いてたら宿題忘れそうだよ!ランドセルに入れておかないと!」「お箸忘れてるよ!」などと子どもが失敗しないように声をかけ続けると、子どもは失敗を経験しません。
親御さんが懸念されている「失敗経験による行き渋りや不登校の予防」にはなるのかもしれません。
しかしながら、これらの声掛けをし続けることで以下のようなことが起こり得ると考えられます。
・学校生活の中で親が前もって声掛けができない状況で失敗経験をして学校が怖くなる
・誰かに指示されないと行動できなくなる
・失敗からどう立ち上がるかが分からない
・失敗=自分はだめな人間 と極端な考え方になる
・年齢相応に自立ができず、他のお子さんとの差ができていった結果学校が怖くなる
などなど。
わたしたちは、様々な経験をして大人になりました。
その経験は成功体験のみではなかったはずです。失敗もたくさん経験して、「次はこうしてみよう」と考えて行動を積み重ねてきたはずです。
むしろ家庭教育で大切なのは、「失敗おめでとう」と言えるくらい、親御さんが子どもの失敗を愛してあげられるかです

何もしないで失敗しないよりも、チャレンジがあっての失敗のほうが尊いです。
失敗は成功の母とも言えますね。
学齢期にお母さんが常に子どもの隣にいて指示してやることは出来ません。
子どもたちは学校環境において楽しいこと、つらいこと、腹がたつこと、悲しいこと、様々なことを体験して社会を知っていきます。
最低限、「人様に迷惑をかけないように」「ルールを守るように」というところをしつけとして伝えておくだけで実は子どもの自立心はぐんと伸びたりします。
もちろん、新小学1年生の場合はある程度親が一緒に時間割をそろえたり、宿題を見てやったり、教えてやることは大切です。はじめてやることについては親が教えてやることは大事です。
本来であればその学年の子であれば自分で考えて行動できる子なのに、親が先回りしてものを言って失敗経験を積ませないようにするのは、実は将来的にみると子どもが本当に困るときがやってくるかもしれません

詳細については、水野先生の書籍やDVDで解説されているPCM11の項目の「先回りしてものを言って子どもの経験を奪わない」をご覧ください

すべてのご家庭にこの理論が当てはまるわけではなく、周囲のサポートが必要なお子さんもいます。
そこについては保護者の皆さんにご判断いただければと思います。
このブログ記事が皆さんのお役に立てれば幸いです

 まいどん先生
まいどん先生
(下のバナーをポチッと応援お願いします
 )
) にほんブログ村
