こんにちは
どんきーです
7月も後半に入りほとんどの学校で夏休みに入っていることと思います
平日の昼間でも子どもたちの楽しそうに遊ぶ声とセミの鳴き声が聞こえてくると本格的に夏に入ったんだなと実感させてくれますね
ぶにん先生(水野先生)がこの間の記事でおっしゃっていたように夏休みは子どもたちが家庭内でいろんなことをしでかしてくれます (笑)
(笑)
これは逆に家庭教育を実践できる良い機会だと私は思います。
現在支援中の方たちは電話カウンセリングや家庭ノートで担当のカウンセラー、アドバイザーとしっかり相談しながら家庭教育をしっかり実践していって頂きたいと思います
さて、今回はそんな夏休みに入る前に復学を果たすことのできた中学生の復学事例の紹介です
中学2年生 不登校 男子 の事例
幼稚園の頃から行き渋りがあり、小学校2年生の時にも登校渋りと母子登校を経験。
その後は順調に登校するも中学1年生の夏休み明けから再び行き渋りが出る。
そこから数えるほどのお休みはありつつも1年生の間は登校。
2年生になり2、3日登校するもその後不登校になる。
支援の開始自体は1年生の12月ごろから家庭教育支援コースにてスタートしました。
その間に家庭教育アドバイザーともに家庭教育を実践していたこともあり1年生の3学期はほとんど休まず登校が果たされていました。しかし、新学年になり、もともと環境変化と長期休み明けの登校に弱かったこともあり、宿題が出来ていないことや風邪や中耳炎をこじらせてしまったために、休まざるをえなくなってしまい、その後家庭内対応を重ねても動くことが出来ずに不登校になってしまったケースでした。
これはのちに分かったことですが、休まざるを得なくなったことで学校にどうやっていけばいいのかわからなくなってしまったようです。
そして、5月から問題解決支援コースにて支援を開始し、復学に向けての支援プランを組み立てていくことになりました。
支援当初の彼の性格分析としては
・いやなことから逃げがち。
・思い込みが強い。
・我慢する力が弱い。
・人に叱られることを極端に嫌がる。
・失敗することを極端に嫌がる。
というところが見られました。
また、学校をお休みしてしまったことで起こっていた問題行動としては
・イライラしたときに物を投げる、叩く、蹴る、イスやタンスを倒すなど、家中を荒らす。
・自分の思い通りにならないと親にいう事を聞かせるためにハンガーストライキをする。
・ハンガーストライキをしている状況で大声で「おなかすいた!」とわめく
・家のルールを守らず自分の要求を押し通す
・兄弟に対して強く当たる。
というところが見られました。
それに対し、家庭内対応の問題点としては
・親が先回りして子の経験を奪いがち。
・子に考えさせる機会が少なく、すぐに指示をしがち。
・父性の立場が低い。
・子に親のイライラをぶつけがち。
以上のことから私は彼は失敗する経験が極端に少ないという事を感じました。
実際12月からの支援で失敗させながら経験を積ませていただいていましたが、それまでの経験値の方が上回っているため半年の支援だけではその傾向を変えていくには時間が短すぎたという現状でした。
ただ、この半年の支援により、家庭内対応の基礎は出来ていたので、あとは彼自身が学校に戻り、社会の中で揉まれ、家庭内対応とカウンセラーのサポートの両方があれば、彼は学校に適応していけるだけの能力はあるだろうと私は判断しました。
ですので、問題解決支援を始めて約1ヶ月という異例のスピードでダイレクトアプローチでのカウンセラーによる直接的な支援を組んでいく事になりました。ダイレクトアプローチは本来、約3ヶ月以上の準備期間をとりますが、このケースでは上記にあるように家庭教育支援にて家庭内対応の基礎をすでに学んでいてもらっていた状態だったので早くにダイレクトアプローチでの支援プランを組めました。
そして、6月に訪問カウンセラーによるダイレクトアプローチ対応に入りました。
続きは、また次回
どんきー(佐藤 博)
宜しければこちらもポチッと応援お願いします。(1日1回クリックを )
)
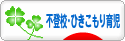
にほんブログ村

どんきーです

7月も後半に入りほとんどの学校で夏休みに入っていることと思います

平日の昼間でも子どもたちの楽しそうに遊ぶ声とセミの鳴き声が聞こえてくると本格的に夏に入ったんだなと実感させてくれますね

ぶにん先生(水野先生)がこの間の記事でおっしゃっていたように夏休みは子どもたちが家庭内でいろんなことをしでかしてくれます
 (笑)
(笑)これは逆に家庭教育を実践できる良い機会だと私は思います。
現在支援中の方たちは電話カウンセリングや家庭ノートで担当のカウンセラー、アドバイザーとしっかり相談しながら家庭教育をしっかり実践していって頂きたいと思います

さて、今回はそんな夏休みに入る前に復学を果たすことのできた中学生の復学事例の紹介です

中学2年生 不登校 男子 の事例
幼稚園の頃から行き渋りがあり、小学校2年生の時にも登校渋りと母子登校を経験。
その後は順調に登校するも中学1年生の夏休み明けから再び行き渋りが出る。
そこから数えるほどのお休みはありつつも1年生の間は登校。
2年生になり2、3日登校するもその後不登校になる。
支援の開始自体は1年生の12月ごろから家庭教育支援コースにてスタートしました。
その間に家庭教育アドバイザーともに家庭教育を実践していたこともあり1年生の3学期はほとんど休まず登校が果たされていました。しかし、新学年になり、もともと環境変化と長期休み明けの登校に弱かったこともあり、宿題が出来ていないことや風邪や中耳炎をこじらせてしまったために、休まざるをえなくなってしまい、その後家庭内対応を重ねても動くことが出来ずに不登校になってしまったケースでした。
これはのちに分かったことですが、休まざるを得なくなったことで学校にどうやっていけばいいのかわからなくなってしまったようです。
そして、5月から問題解決支援コースにて支援を開始し、復学に向けての支援プランを組み立てていくことになりました。
支援当初の彼の性格分析としては
・いやなことから逃げがち。
・思い込みが強い。
・我慢する力が弱い。
・人に叱られることを極端に嫌がる。
・失敗することを極端に嫌がる。
というところが見られました。
また、学校をお休みしてしまったことで起こっていた問題行動としては
・イライラしたときに物を投げる、叩く、蹴る、イスやタンスを倒すなど、家中を荒らす。
・自分の思い通りにならないと親にいう事を聞かせるためにハンガーストライキをする。
・ハンガーストライキをしている状況で大声で「おなかすいた!」とわめく
・家のルールを守らず自分の要求を押し通す
・兄弟に対して強く当たる。
というところが見られました。
それに対し、家庭内対応の問題点としては
・親が先回りして子の経験を奪いがち。
・子に考えさせる機会が少なく、すぐに指示をしがち。
・父性の立場が低い。
・子に親のイライラをぶつけがち。
以上のことから私は彼は失敗する経験が極端に少ないという事を感じました。
実際12月からの支援で失敗させながら経験を積ませていただいていましたが、それまでの経験値の方が上回っているため半年の支援だけではその傾向を変えていくには時間が短すぎたという現状でした。
ただ、この半年の支援により、家庭内対応の基礎は出来ていたので、あとは彼自身が学校に戻り、社会の中で揉まれ、家庭内対応とカウンセラーのサポートの両方があれば、彼は学校に適応していけるだけの能力はあるだろうと私は判断しました。
ですので、問題解決支援を始めて約1ヶ月という異例のスピードでダイレクトアプローチでのカウンセラーによる直接的な支援を組んでいく事になりました。ダイレクトアプローチは本来、約3ヶ月以上の準備期間をとりますが、このケースでは上記にあるように家庭教育支援にて家庭内対応の基礎をすでに学んでいてもらっていた状態だったので早くにダイレクトアプローチでの支援プランを組めました。
そして、6月に訪問カウンセラーによるダイレクトアプローチ対応に入りました。
続きは、また次回

どんきー(佐藤 博)

宜しければこちらもポチッと応援お願いします。(1日1回クリックを
 )
) にほんブログ村
